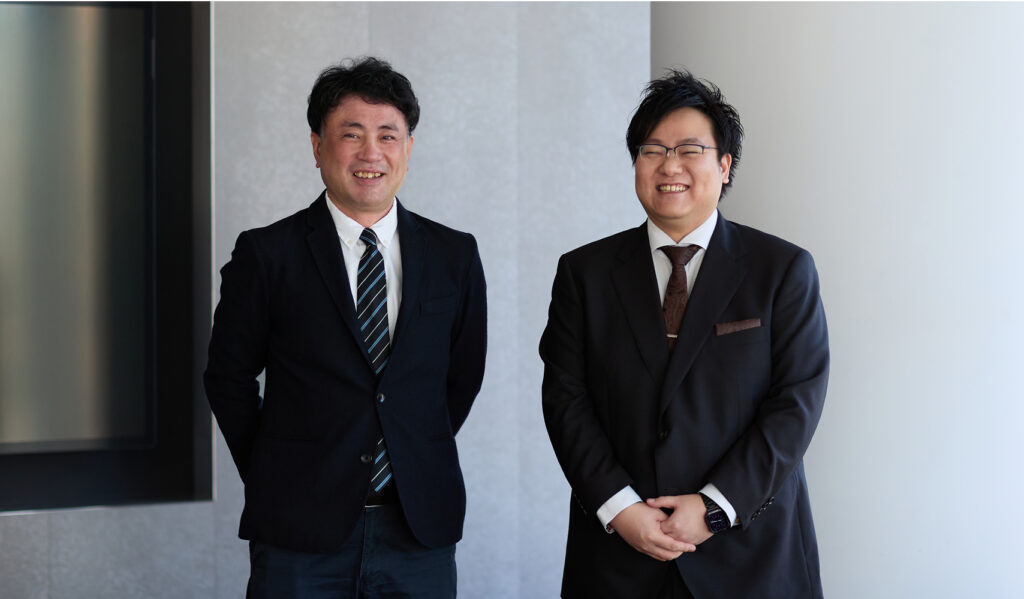ここ数年で社会も市場も大きく変化する中、御グループの組織のあり方もパラダイムシフトを迎えました。改めて組織変革の背景や経過を教えてください。
跡部様:大きく分けて二つあります。一つ目はコーポレート全体の改革の領域です。当社は現在、国内外の親会社から関連会社まで含めると、約600社で運営しています。そのためグループ全体を見渡せる人財が不足し、全体の指針を統一することが難しいという局面が出てきていました。そこで最上位にホールディングス会社を設立するとともに、海外ビジネスと国内ビジネスを担う2つの事業会社を配置するという三社体制を導入しました。NTTデータグループ全体での事業再編に際し、グローバル本社としての在り方を再構築しようという、ある意味今まで手薄だった状況から大きなチャレンジに乗り出したわけです。
二つ目は、グローバルガバナンス本部の自組織の課題解決です。法務、リスクマネジメント、コンプライアンスなどの仕組みを、再編を機に改めて整備する必要がありました。コーポレートとしての通常業務から踏み出したクリエイティブかつスピードが求められるもので、組織設計・人財配置から見直さなければならないチャレンジとなっています。
これらは全体として影響範囲が極めて大きく変革も難しい領域ですが、その対応をプロレドにも支援いただいています。

御社はこれまでの歴史も長く、膨大な関連会社と連携しながらグローバルで飛躍的成長を続けています。ガバナンスを少数精鋭の部門がまとめていくためには日々多くの複雑な課題解決が求められると推察しますが、特に意識されていることはありますか。
跡部様:感覚的なお話になりますが、私たちは常に自分たちが過渡期にあることを意識しています。多種多様な変化に対応していかなければなりません。もしそういった部分で自分たちの組織に強みがあるとすれば、法務人財をはじめとする様々な専門スキルや卓越したノウハウを持った人財で組織が構成されている点でしょう。
まずは法務人財を中心に、グループマネジメントやリスクマネジメントといった隣接するコーポレートファンクションに輪を広げ、組織のシナジーを幅出ししていっています。そのために、これまで事業部ごとに固定化されていた縦割りの壁を取り払い、意識や事業のボーダーを壊してから再構築し、それぞれの人財が持っている専門スキルを全体のために活用する、そんな取り組みを進めています。またその過程では外部からの視点も必要だと考えています。
現代の潮流として、例えば生成AIなどの最新テクノロジーが急激に台頭していますが、御社は日本の中でも強くそれを牽引し、支えているお立場にあります。そうした先進的事業・取組を加速させていくうえで、グローバルガバナンス機能として意識されていることはありますか。
跡部様:はい、そこについては他社に先駆けて数年前から取り組みを始めており、「AIガバナンス室」という部署を2024年度に設置し、AIビジネスの発展と同時にAI倫理のリスクとのバランスを事業として担保していく営みを行っています。今まではAI技術の開発を各部門がそれぞれ推進している一方、全体としてどのようにコントロールし、リスクマネジメントしていくべきかが課題となっていました。現在は、前述した当本部の法務人財と技術開発人財とを組み合わせた融合組織を立ち上げ、両者の連携のもと、事業発展に貢献するという段階に進んでいます。

今回の御社とプロレドのお付き合いは2024年から始まりました。もちろん、それ以前にも各部門やプロジェクト単位で部分的な関わりはありましたが、今回全社的な課題解決に向けて弊社を選んでいただいたのはなぜでしょうか。
跡部様:もちろん、他社と違って「毎週顔を合わせ、スコープやアジェンダそのものから議論してくれる」という点に安心感、親しみを感じた部分もありました。特にPJ初期段階では、それが大きなサプライズでした。一方で、いつまでも話し合いを続けるだけではなく、必ず先回りしたアウトプットを出してくれる。御社の「コンサル」としての基本姿勢がまさにそうであると気付いたとき、同調するように「一緒に試行錯誤を重ね、結果を出そう」という気持ちになっていったのだと思います。実際、本当に最初の頃は毎週のように顔を出していただいていましたよね。契約の話もしないままに(笑)。
まさに私たちの基本姿勢は「価値 = 対価」です。つまり「何か《成果(価値)》を出して、そこで初めて《報酬(対価)》」をいただく」。そのあたりについてはご満足いただけていますでしょうか。
跡部様:他ファームでは、まず価格交渉をし、次に契約期間や業務内容を決めてから仕事が始まりますよね。
プロレドはその順序が全く逆で、毎週のように顔を出していただき、こちらから相談事などをしても、「成果が出なければ報酬はいらない」とおっしゃる。もう少し踏み込んで言えば、「対価を得るためには、先に価値を提供するのが当たり前だ」と考えをお持ちですよね。その対価(報酬)も、実際の成果に見合った正当な価格を提示してくれているように思います。コンサルティング・ファームとしてずいぶん珍しいスタンスだなあ、とは思いました(笑)。
そして実際にその仕事ぶりにはとても満足しています。例えば、社内のさまざまな立場の人間に対し、本音を引き出すようなインタビューをしてくださいました。そうやって、実際の声を丁寧に集めていただき、中長期の組織戦略策定や組織変革施策に落とし込むことができました。私たちだけではできない価値創出でした。

「成果を出してから報酬をいただく」という方針に加え、支援スコープに縛られすぎず、ビジネスの前後を含めて長く親しくお付き合いできるよう努めています。私たちはこれを「伴走型コンサル」と呼んでいるのですが、そういった形であっても、「前後に」「外部から」第三者であるコンサルタントを入れることに抵抗はありませんでしたか。
跡部様:もしかしたら、当初は抵抗感を持つ社員もいたかもしれません。しかし私たちの組織はあまりに大きく、複雑になりすぎていて、社内の人間では誰もそれを紐解くことができませんでした。皆「変わりたい」「変わるべきだ」と思ってはいたのですが…。
そこで、自分の部署や自分のプロジェクトとは利害関係のない「外部の立場」を取り入れることが必要だろう、という結論に至りました。また結果として、御社が「経営全体を分析する力」と研ぎ澄まされた専門知識を持っておられたことが大きかったように思います。私たち社内の人間は自分の仕事についての専門性は持っていましたが、「組織全体を見通す」という視座を持った人間が非常に少なかったのです。
御社では他にも多くのコンサルティング・ファームとお付き合いがあると思います。その中で私たちプロレドにはどのような印象をお持ちでしょうか。
跡部様:「コンサルタント」というと、もしかしたら「上から目線の人々がいきなり指示を出してくる」という印象を持たれることがあるかもしれません。しかしプロレドはそうではなく、まず現場に入ってきて私たちと一緒に仕事を進めてくれました。そうすると、現場の中からも「お、この人たち頑張ってくれるな!」と士気が上がり、前向きになってくれる変化が生まれました。「偉そうで面倒くさい人たちがやってきたと思っていたら、意外にも自分たちと同じように泥臭い仕事を一緒にやってくれている」そんな意外性が良い方向に働いたと思います。
もちろん、御社としては現場に入ることで「MTGしているだけでは見えてこない、いろいろな潜在的課題を見つける」という意図もあったのかもしれません。しかしそれ以上に現場も経営層も「一緒に走ってくれている」という嬉しさのほうが大きかったですね。
最後に話は変わりますが、これからの時代に必要となってくるのは、どのような人財だと思われますか。
跡部様:まず、市場環境が大きく変わっていく中で、単に「専門知識を持っている」「ガバナンスに精通している」というだけでは苦しくなってくると思います。求められるのは、包括的な力を持つ人財、少なくともそれにトライできる人財です。
もうひとつ、多様な経験を積んでいる人、またはこれから多様な経験を積んでいくのを厭わない人、でしょうか。私たちのように組織設計に関わる立場として、さらにこまかく言えば人事として、数多くの社員の適性を考えながら配置や異動を行う中で、「このポジションはイヤだ」というのではなく「その意味は何だろう」「自分の将来にどう結びつくのだろう」と考えてくれるような人財の方が中長期的に大成する確率が高いと感じます。自身を俯瞰し、成長に向かって積極性や考え方の多様性を発揮できる方が、これからの時代により必要とされるでしょう。
今、新卒採用の方にも中途採用の方にも「短期間でキャリアを積み上げていきたい」「そのために必要なスキルや資格を、具体的に教えてほしい」とおっしゃる方が非常に多い。しかし、昨今の急激な社会変化の中、そんな目先のことばかりを考えていても、その人のためにはならないと思っています。そうではなく、「最終的に自分がどう羽ばたいていけるか」ということに目を向けてほしい。会社としては、いつかは社員のみなさん全員に、「経営人財」となってほしいと思っています。そのためには、こうした広い視野と柔軟な姿勢を持っていてくれることを期待し、また私たちも全力でサポートしていきます。