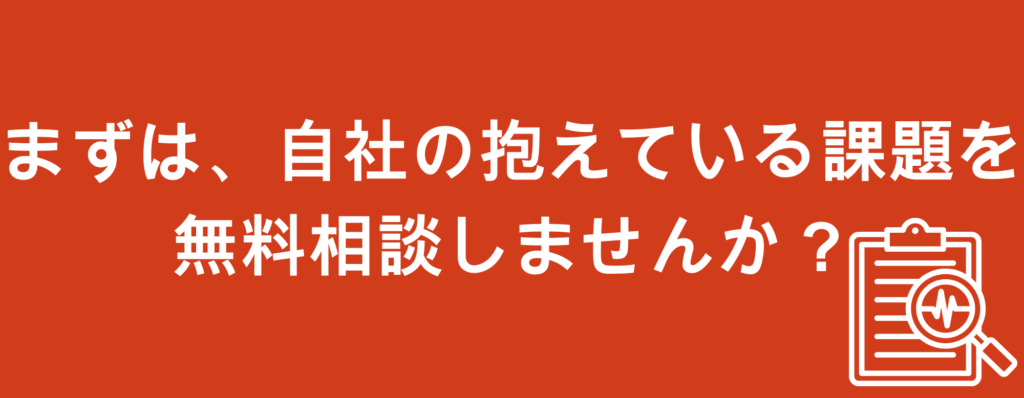物流業界は、2024年問題を契機に大きな転換点を迎えています。トラックドライバーの時間外労働規制強化による輸送能力の低下やコスト上昇といった課題が浮き彫りとなり、従来の商習慣や物流構造の見直しが急務となっています。その中で、新たに制定された「新物流効率化法」は、物流の適正化と生産性向上を目的としており、企業に対し「CLO(Chief Logistics Officer)」の選定や中長期計画の策定を義務付けました。これにより、物流は単なるコスト管理の領域を超え、企業の競争力を左右する重要な経営課題として位置づけられるようになっています。
本記事では持続可能な物流の実現に向けて、戦略的にどのように対応すべきか、最新の動向を踏まえて具体的に解説します。次世代に向けた物流戦略を検討している方は、ぜひご一読ください。
SCM/3PL/物流のお悩みを解決したい方へ

プロレド・パートナーズでは、現状把握から施策の立案・実行まで一貫したサポートが可能となります。SCM改善について皆様からのご相談をお待ちしております。
新物効法施行に向けた流れ

物流業界は今、かつてない変革の時を迎えています。その契機となったのが「2024年問題」です。トラックドライバーの時間外労働の上限規制により、輸送能力の不足や物流コストの上昇といった課題が表面化しつつあり、これに対応するために物流業界全体で商習慣の見直しが求められるようになりました。従来の物流構造では、長時間の荷待ちや不適切な契約の取り決めがドライバーの負担となっていましたが、これらの課題を改善し、より効率的で持続可能な物流の実現を目指す流れが加速しています。
このような習慣の変革を制度的に後押しするために制定されたのが「新物効法」です。この法律は、荷主企業に対し、物流の効率化や合理的な運営を促すことを目的としており、企業には主に以下の3つの対応が求められています。
1.物流の効率化と生産性向上
トラックの積載率向上や共同配送の推進など、無駄のない物流体制の構築
2.ドライバーの労働環境改善
荷待ち時間の削減や契約条件の適正化など、現場負担の軽減と健全な運用の確保
3.カーボンニュートラルへの対応
CO₂排出量の可視化や削減施策の実行など、環境配慮型の物流への転換
これらの取り組みを戦略的かつ継続的に実行するためCLO(Chief Logistics Officer)の選定が法律で義務化されました。 CLOは企業の物流戦略を統括し、部門を横断した連携やデータ活用を通じて、持続可能な物流体制の構築をリードする役割を担います。
言い換えれば、CLOに求められるのは、荷主企業としての責任を戦略に落とし込み、実行に移すことです。物流が企業の競争力に直結する現代において、CLOの果たすべき役割は極めて大きく、効率性や環境対応、さらにはデジタル技術の活用を含めた多角的なアプローチが不可欠となっています。
このように、「2024年問題」を契機として、商習慣の見直しが求められ、さらにその変革を推進するために「新物効法」が成立するという流れの中で、企業の物流戦略は根本的な転換を迫られています。これまで単なるコスト管理の一部と考えられることが多かったサプライチェーン・物流戦略が、経営の中核的な要素として位置づけられる時代へと移行しているのです。
商習慣の見直し
従来の物流業界では、荷主企業が優位な立場にあり、ドライバーの荷待ちや荷役時間が長時間に及ぶことで、労働環境の悪化や物流の効率低下を招いていました。こうした課題を解決し、持続可能な物流を実現するため、政府は「物流の適正化・生産性向上に向けたガイドライン」を策定し、荷主に対し物流の効率化を求めました。
このガイドラインでは、荷主と物流事業者の協力による物流業務の合理化が求められ、特に荷待ち・荷役時間の削減が最優先課題とされています。「1運行当たりの荷待ち・荷役等時間の2時間以内ルール」が導入されており、時間管理の徹底が重要な取り組みとされています。また、適正な運送契約の締結も重要視され、契約の書面化や「運賃」と「料金」の分離によって、ドライバーの適正な労働環境が確保されるよう求められています。
新物効法とは

新物効法とは、物流業務の合理化と生産性向上を目的とし、特定荷主に対して「中長期計画の策定」「定期報告の実施」「CLOの選定」を義務付けるものです。これにより、企業の物流戦略は単なるコスト削減から、全体最適を目指すものへとシフトしていくことが想定されます。
この法律の目的は、荷主と物流事業者の協業を促進すること、トラックドライバーの労働環境を改善すること、サプライチェーン全体の最適化を図ることにあります。さらに、物流DX(デジタルトランスフォーメーション)の促進も視野に入れられており、物流業界の近代化が進められようとしています。
中長期計画の策定
特定荷主は、物流の合理化と効率向上を目的とした中長期計画を作成し、所管大臣に提出する必要があります。この計画には、荷待ち・荷役時間の削減策、積載効率向上に向けた取り組み、サプライチェーン全体の最適化施策などが含まれます。
定期報告の実施
特定荷主は、中長期計画の実施状況を定期的に報告する義務があります。報告内容には、物流効率化の進捗状況、荷待ち時間の短縮効果、積載率の向上などが含まれます。この報告は、国が物流改善の評価を行う基礎資料となり、違反が発覚した場合には指導・勧告が行われる可能性があります。
CLO(物流統括管理者)の選定
特定荷主は「CLO(Chief Logistics Officer)」を選定し、企業全体の物流業務を統括する役割を担わせることが義務付けられます。CLOは、物流の合理化を推進し、持続可能な輸送体制を構築するための責任を負います。具体的には、中長期計画の策定、荷待ち・荷役時間の削減施策の実施、物流のデジタル化推進などの業務を担当します。
次世代物流スタンダードの誕生
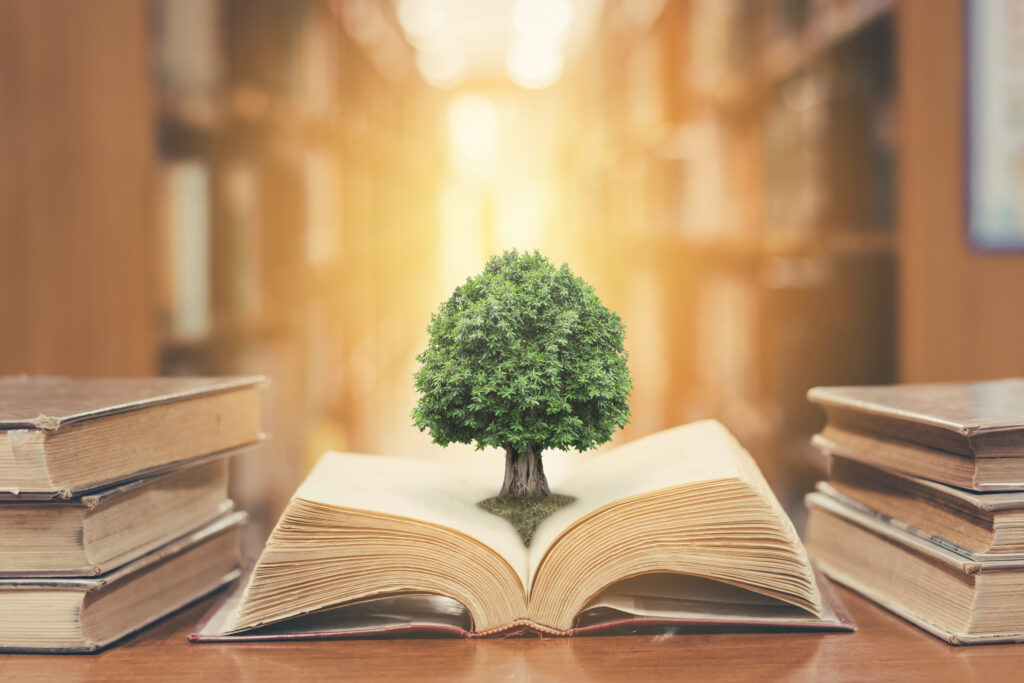
次世代の物流スタンダードは、従来の商習慣や物流の枠組みを根本から見直し、より効率的かつ持続可能な物流を実現するものです。
商習慣の変化
これまでの物流業界では、経験や勘に頼った意思決定が一般的でした。しかし、今後はデータの活用が進み、AIやビッグデータを駆使した合理的な判断が物流の意思決定に不可欠となります。リアルタイムの配送データや需要予測に基づき、最適なルート設定や在庫管理が可能となることで、物流の無駄が大幅に削減されるでしょう。
従来は営業や製造が優先され、物流はその後に調整されるという構図が一般的でしたが、今後は物流の効率性を考慮した全体最適の視点が重視される時代へと移行していきます。そして、この全体最適を実現する鍵となるのが、データドリブンによる意思決定の仕組みです。データを基盤に、各部門を横断した調整や迅速な判断が可能となり、物流を起点とした生産計画や販売戦略が策定されるようになります。物流は経営戦略の中核として再定義され、その重要性はますます高まっていくでしょう。
さらに、これまでの荷主優位の取引関係にも変化が生まれ、物流事業者との協業体制が強化されることで、公正かつ持続可能なビジネスモデルの構築が進むと考えられます。
物流オペレーションの変化
物流の運営方法も大きく変革されます。従来の倉庫や配送における生産性の低さが、自動化技術の導入によって大幅に改善されることが期待されています。たとえば、倉庫内ではロボットやAIによる自動仕分け、無人搬送システム(AGV)の活用が進み、物流業務の効率化と生産性の向上が実現されます。配送の分野でも、ドローン配送や自動運転トラックの導入が加速し、ラストマイル配送の効率化と高い生産性の確保が進むと考えられています。
また、属人的な業務プロセスから脱却し、リアルタイムデータを活用した最適ルート設定へと移行する動きが活発化しています。GPSとAIを組み合わせた動態管理システムにより、トラックの位置情報や道路の混雑状況を即座に反映したルート最適化が可能となり、遅延の最小化や配送効率の最大化が実現されます。
さらに、低積載率の輸送が見直され、共同配送や積載率の向上が進みます。複数の荷主が共同で物流リソースを活用し、効率的な輸送ネットワークを構築することで、車両の稼働率を向上させ、物流コストを削減する取り組みが本格化するでしょう。
契約・コストの変化
契約やコストの面でも大きな変化が予想されます。これまで不明確であった料金体系が、実際の業務内容に応じた透明性のある契約へと整理され、適正な運賃や料金が設定されるようになります。特に、従来は運賃と荷役作業などの付帯業務が曖昧な形で契約されていましたが、今後は「運賃」と「料金」を明確に区別し、適正な対価を設定する動きが強まるでしょう。
また、物流コストについても、これまでのように安価な料金単価を求めるのではなく、物流の効率化による適正単価の確保が求められるようになります。単なる価格交渉ではなく、物流の全体最適を考慮したコスト設定が進むことで、サプライチェーン全体の最適化へとシフトしていきます。
このように、次世代の物流スタンダードは、従来の商習慣や物流構造を根本的に変革し、データ活用、技術革新、協業の強化を通じて、より持続可能で効率的な物流環境を実現するものとなります。
まとめ
新物効法の施行により、企業はCLOの選定を通じて、物流戦略を全体最適へとシフトする必要があります。これまでのように物流を単なるコスト削減の一環と捉えるのではなく、持続可能なサプライチェーンの中核として再評価することが求められます。物流の効率化は、企業の収益向上だけでなく、環境負荷の軽減や社会的責任の観点からも重要な役割を果たします。
この全体最適の実現には、現場の状況を可視化し、根拠に基づいた意思決定を行うためのデータドリブンなアプローチが不可欠です。そして、その中心的な役割を担うのがCLOです。CLOは、物流を経営戦略の視点から統括し、部門横断での最適化をリードする存在として、今後ますます重要性を増していくでしょう。
2026年のCLO選任と中期経営計画提出に向けて何から対応すればいいかお困りの際はプロレド・パートナーズにご相談ください。CLOのデータドリブン経営を推進していくためのご支援を致します。
SCM/3PL/物流のお悩みを解決したい方へ

プロレド・パートナーズでは、現状把握から施策の立案・実行まで一貫したサポートが可能となります。SCM改善について皆様からのご相談をお待ちしております。