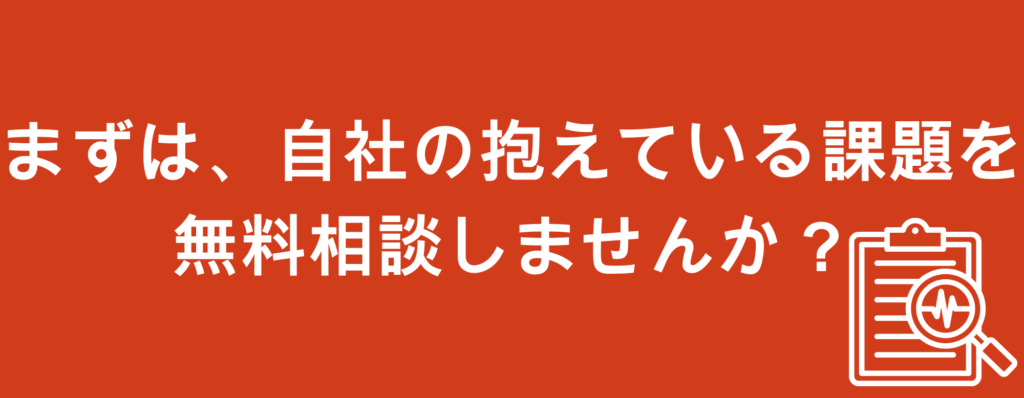2026年から企業に対して「CLO(Chief Logistics Officer)」の選任が義務化されます。これにより、企業の物流戦略は単なるコスト管理から経営の中核へとシフトすると考えられます。しかし、物流業務の複雑化が進む中で、CLOが単独でその責務を担うには限界があり、効果的な支援体制の構築が不可欠です。その解決策として注目されるのが、CLOを補完・支援する「CLOSO(Chief Logistics Officer Supporting Office)」の導入です。
本記事では、CLOSOが果たす役割や導入のステップについて詳しく解説します。CLOSOは単なる補助機関ではなく、物流のイノベーションを推進し、企業の競争力を高めるための中核的な組織です。データ活用・戦略推進・関係者調整などを担い、CLOが本来の役割に集中できる環境を整えることで、物流改革のスピードを加速させます。今後、物流改革を成功に導くために、企業がどのようにCLOSOを活用すべきか、その具体的な戦略を詳しく見ていきます。
SCM/3PL/物流のお悩みを解決したい方へ

プロレド・パートナーズでは、現状把握から施策の立案・実行まで一貫したサポートが可能となります。SCM改善について皆様からのご相談をお待ちしております。
CLO選任の義務化とその課題

2026年、企業は「物流統括管理者(CLO:Chief Logistics Officer)」の選任を義務付けられることが決定しました。この規制は、物流の効率化と持続可能な改革を推進することを目的としており、企業にとってCLOの適切な配置や役割の確立が大きな課題となっています。CLOは、企業の物流戦略全体を統括し、サプライチェーン全体の最適化を図る責任を負いますが、その役割は広範にわたり、業務を一手に担うには限界があります。
物流は、企業の競争力を左右する重要な経営機能の一つであり、近年のEC市場の拡大やグローバル化の進展により、その重要性はますます高まっています。消費者の需要が多様化し、迅速な配送が求められる中で、企業は物流の最適化とコスト削減の両立を迫られています。
その中でCLOには、物流改革の推進者としてのリーダーシップ、データドリブンによる意思決定力、そして社内外の関係者との円滑なコミュニケーション力という、3つの力が求められます。これらの力を発揮し、全社的な物流戦略を成功に導くには、現場レベルから経営レベルに至るまでの情報を横断的に捉え、構造的な課題を把握することが不可欠です。
まず取り組むべきは、現状の物流の可視化と課題の把握です。膨大な調査と精緻な分析を通じて、ボトルネックを特定し、改善の優先順位を定める必要があります。そのためには、データに基づいた定量的なアプローチが不可欠です。特に、大企業においては物流の構造が複雑であるため、CLOが一手に引き受けるのは現実的ではなく、専門的な支援体制やデータ分析基盤の整備が求められるでしょう。
CLOの選任について

海外では、日本以上にCLO(または類似する役職)が企業経営に深く関与する傾向があります。Apple、Walmart、General Motorsなど多くの海外企業では、物流またはサプライチェーン部門出身者がCEOに就任しており、物流の重要性が企業経営の中核に組み込まれています。これは、物流が単なるコストセンターではなく、企業の競争力を左右する重要な要素であることを示しています。
日本企業におけるCLOの選任パターン
一方、日本企業では、CLOの選任方法に大きく分けて三つのパターンが見られます。
① 物流部門長の昇格
日本企業におけるCLOの選任方法において最も多く見られるのが「物流部門長の昇格」です。現場起点で物流を深く理解している点は大きな強みであり、特に倉庫業務の生産性改善や配送業務の効率化、ドライバーの労働環境改善など、現場レベルでのオペレーション改革を主導できる点が注目されます。
一方で、CLOには全社的なサプライチェーンマネジメントの再構築や、経営戦略との整合を図る役割も求められます。そのため、物流部門出身者がCLOに就任した場合、戦略構想力や経営視点の不足がボトルネックとなるケースも見られます。例えば、属人的な判断に依存しすぎてデータドリブンな改革が進まない、他部門との意思決定の整合に時間がかかるなどの課題が典型です。
このようなギャップを埋めるには、就任前の経営教育プログラムの整備や、経営企画部門・事業部門へのローテーションを経た上でのCLO任命といった準備が有効です。CLOを単なる「物流の責任者」ではなく、経営の一角として機能させるための制度設計が、今後の企業競争力を左右すると言えるでしょう。
② 営業系役員の兼務
CLOのもう一つの典型的な選任パターンは、営業、調達、製造など他部門の担当役員が兼務する形式です。このアプローチでは、サプライチェーン上流との連携がスムーズであり、調達計画や製造計画、販売施策と連動した物流改革が実現しやすいという強みがあります。特に、物流施策と営業・製造戦略が一体化することで、SCM全体の最適化を通じた売上向上やコスト効率化が期待されます。
一方で、兼務CLOには物流に関する実務的・技術的な理解が十分でないという課題が発生します。現場で何がボトルネックになっているのか、どこに改善の余地があるのかを正確に把握するには、ある程度の現場知識や実務経験が不可欠です。これが不足すると、改革が表面的なものにとどまり、物流部門の巻き込みが不十分となるリスクがあります。
さらに、兼務であるがゆえに、物流改革に投入できる時間やリソースが限定的になる傾向も否めません。改革スピードの鈍化や、推進力の分散といった問題も懸念されます。これを補うには、物流部門側からCLOをサポートする専門性の高い人材を機能として配置する体制が必要となります。
CLOを営業や製造の延長線上で位置付けるのではなく、ロジスティクスの専門領域として戦略的に捉える姿勢が、今後の企業経営に求められています。
③ 将来のCEO候補からの選任
近年、一部の日本企業では、CLO(Chief Logistics Officer)ポストを将来のCEO候補の育成機会として位置づける動きも見られます。このアプローチの最大の特徴は、全社経営戦略と物流改革を統合的に推進できるポテンシャルを持つという点にあります。
とりわけ、グローバル展開やオムニチャネル化を進める企業においては、物流が単なるコストセンターではなく、競争優位の源泉となる領域へと進化しています。こうした状況下では、CLOに就任したCEO候補がサプライチェーン全体の可視化・最適化を指揮することで、企業全体の経営効率や機動力を高めることができます。
また、営業や製造といった他部門の経験がなくとも、物流とサプライチェーンの現場から「モノの流れ」「事業の構造」を体系的に理解する機会は、次世代経営人材の視野拡張において非常に有効です。経営資源の循環構造をリアルに体感できることで、全社的な意思決定の解像度が高まります。
ただし、経営視点を持つ候補者がCLOを担う際には、現場業務への理解が不足するケースが課題となります。特に物流のデジタル化や業務変革(DX)を進めるフェーズでは、現場との双方向のコミュニケーションと信頼構築が不可欠です。適切なサポート体制(例:現場経験豊富な副担当の配置や、外部専門人材の活用)を整えることで、トップダウンと現場実行のギャップを埋めることが求められます。
この選任パターンは、CLOを単なる機能責任者にとどめず、「経営を担うC-suiteの一角」として戦略的に活用する発想を持つ企業において、今後ますます重要性が高まると考えられます。
上記①②③いずれのパターンにおいてもCLOの選任にはメリットと課題が存在します。企業の物流戦略を強化し、サプライチェーンの全体最適を実現するためには、CLOを単なる物流管理者としてではなく、経営戦略の中核として位置づけることが必要です。そのため、CLOを補完・支援する組織として、「CLOSO(Chief Logistics Officer Supporting Office)」の設置が考えられます。
CLOSOとは
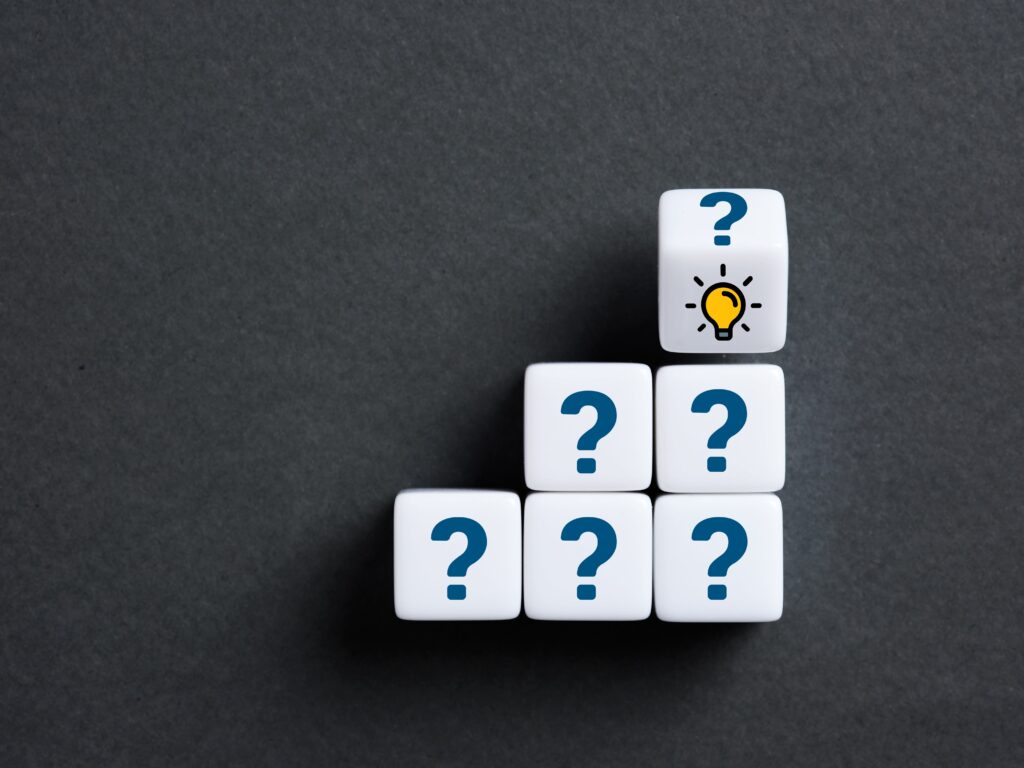
CLOSO(Chief Logistics Officer Supporting Office)とは、CLOを補完・支援し、物流改革を実行力のあるものとするための専門組織です。
複雑化・高度化が進む物流領域において、CLOが戦略の立案から実行までを一手に引き受けるのは現実的ではありません。そこでCLOSOは、データ分析、戦略策定、関係者調整などの実務を担うことで、CLOが本来の意思決定に専念できる環境を整えます。
CLOSOの役割は、単なる補助機関にとどまらず、物流のイノベーションを主導する機関としても機能します。例えば、物流ネットワークの再構築、AIやIoTを活用した配送の最適化、倉庫管理の自動化推進など、最新のテクノロジーを活用した戦略立案を担うことが想定されます。これにより、CLOは経営層と連携しながら、企業の中長期的な物流戦略の策定と実行に集中できるようになります。
本稿では、日本におけるCLO選任パターンを踏まえつつ、CLOSOの必要性と導入ステップについて詳しく解説します。CLOに負担が集中することなく、企業全体として物流改革を推進できる体制を構築するための具体的なアプローチについて考察していきます。
CLOSOの役割
CLOSOの役割は大きく三つに分類されます。
① データ活用・物流KPIの可視化
- CLOの意思決定を支援するため、データに基づいた分析と判断を行う
- 物流・サプライチェーン関連データを統合し、KPIとして可視化することで経営層に対する情報提供を強化
- 現状分析や問題特定、改善策の策定をサポート
② 戦略策定・物流改革の推進支援
- 戦略的観点から物流改革を総合的に推進し、企業全体の最適化を図る
- CLOが定めた物流戦略の実行支援として、施策の具体化やスケジュール策定、関係者調整を行う
- 物流業務の再設計や標準化、プロセス改善を推進し、実行可能な施策として定着させる
- CLOが主導する改革に対して、実務レベルでのサポートを提供し、CLOの業務負担を軽減
③ 社内外の調整・商慣習の変化対応
- 物流改革に伴う関係者間の負担を軽減し、スムーズな進行を支援
- 営業・調達・生産部門などの社内部門との連携を強化し、物流最適化を企業全体の改革として推進
- 荷主や物流事業者との交渉、契約管理を支援し、適正運賃の確保や荷待ち時間の削減などの施策を実行
- CLOの戦略実行を後押しするため、CLOSOが物流改革のプロジェクト管理を担当し、停滞を防ぐ
CLOSO導入の実践ステップ

CLOSO導入は、4つのステップを踏んで進めます。これにより、CLOの業務負担を軽減し、企業全体の物流戦略を強化することが可能となります。
ステップ1:CLOの業務範囲の整理と役割の明確化
まず、CLOの業務範囲を整理し、物流戦略を立案する企画業務とオペレーション業務の切り分けを明確にする必要があります。CLOは、企業全体の物流戦略の策定やサプライチェーン全体の最適化を担う一方で、日々のオペレーション管理やデータ分析、社内外の調整などの実務レベルの業務はCLOSOが担う体制を構築します。この整理を行うことで、CLOは経営層との調整や長期戦略の策定に集中できるようになります。
この段階では、既存の物流体制の課題を洗い出し、CLOとCLOSOの役割分担を文書化して明確に定義することが重要です。また、他部門との関係性を整理し、営業・調達・生産部門との連携方法も明確にすることで、CLOSOが円滑に機能する基盤を整えます。
ステップ2:CLOSOチームの組成と人材の配置
次に、CLOSOチームを組成し、社内リソースを活用しながら専門人材を配置します。CLOSOには、以下のようなスキルを持つメンバーが求められます。
- データアナリスト:データや情報の調査・収集・分析を担当し、BIツールを活用して可視化を行う
- サプライチェーンマネージャー:物流プロセス全体を統括し、最適化の推進を担当
- DX推進担当者:最新のデジタル技術を活用し、AIやIoTによる物流効率化をリード
- オペレーション管理担当:物流KPIの設定・管理、物流事業者との調整、契約管理を実施
必要に応じて外部の専門家やコンサルタントの支援を活用し、スムーズな立ち上げを進めます。企業によっては、他部門のリソースを活用しながら小規模で始め、徐々に拡張する形でCLOSOを構築するのも有効です。
ステップ3:データ統合とリアルタイム管理の実装
CLOSOが効果的に機能するためには、物流データ基盤を整備し、リアルタイムでの可視化を実現することが不可欠です。これには、以下の取り組みが必要です。
- データ統合基盤の構築:企業内外の物流データを統合し、一元管理するシステムを導入
- BIツールやダッシュボードの活用:リアルタイムで物流KPIを可視化し、経営層と現場の意思決定をサポート
- AI・機械学習の導入:需要予測や配送ルートの最適化を実施し、コスト削減と効率向上を実現
- IoTデバイスの活用:トラックの動態管理や倉庫内の在庫状況をリアルタイムで把握
このデータ基盤を活用することで、CLOSOは物流業務の改善点を迅速に特定し、KPIの達成状況を適切に管理できます。また、リアルタイムデータを活用することで、異常発生時の即時対応が可能となり、サプライチェーンの安定性が向上します。
ステップ4:物流改革のPDCAサイクルの確立
最後に、物流改革のPDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを確立し、継続的な改善を進めます。
- Plan(計画):物流戦略の立案、KPIの設定、改善施策の策定
- Do(実行):CLOSOを中心に、データをもとに具体的な物流改革を実施
- Check(評価):KPIの進捗をリアルタイムでモニタリングし、問題点を特定
- Act(改善):課題を修正し、次の施策へと反映
このサイクルを回しながら、物流戦略の最適化を図ることで、企業の競争力を強化できます。CLOSOの役割は、CLOが策定した戦略を実行し、改善サイクルを回し続けることにあります。そのため、定期的な会議やレビューを実施し、CLOとの密な連携を図ることが重要です。
今後の展望

CLOSOを導入することで、物流の意思決定が迅速化され、戦略的な物流改革が加速します。企業は、物流業務を単なるオペレーションとして捉えるのではなく、経営戦略の一環として位置付け、CLOとCLOSOが一体となって物流最適化を進めることで、競争力の強化が可能となります。
今後、物流業界ではさらなるデジタル化と自動化が進む中で、CLOSOの役割はより重要になっていきます。物流の複雑性が増す中で、CLOが全てを担って改革を進めるのは難しくなり、CLOSOの支援体制が不可欠となるでしょう。
CLOSOの導入は、企業の物流管理を次のステージへと引き上げる重要なステップとなります。データ活用、戦略推進、業務最適化を支援するCLOSOの仕組みを整えることで、持続可能な物流体制の構築が実現されるでしょう。これはまさに、変化の激しい時代に対応する次世代物流スタンダードの中核を成す取り組みであり、企業が将来にわたって競争優位を確保するための鍵となります。
まとめ
物流業界は、労働力不足や環境対応など深刻な課題に直面しており、従来の延長では対応できない抜本的な改革が求められています。企業にとって物流は、コスト削減の対象ではなく、経営戦略の重要な柱です。その中でCLOは、全社的な物流戦略を統括する要となりますが、改革を着実に進めるには実務面を担う体制が必要です。CLOSOを導入することで、戦略の実行力が高まり、意思決定の質とスピードが向上し、持続可能な次世代物流体制の構築が可能となります。
プロレド・パートナーズでは、CLOによるデータドリブン経営の実現はもちろん、それを現場で支えるCLOSO体制の構築まで、一貫したご支援が可能です。2026年のCLO選任と中期経営計画の提出を見据え、何から着手すべきかお悩みの企業のご担当者様は、物流を経営戦略の中核に据えるための第一歩として、ぜひご相談ください。
SCM/3PL/物流のお悩みを解決したい方へ

プロレド・パートナーズでは、現状把握から施策の立案・実行まで一貫したサポートが可能となります。SCM改善について皆様からのご相談をお待ちしております。