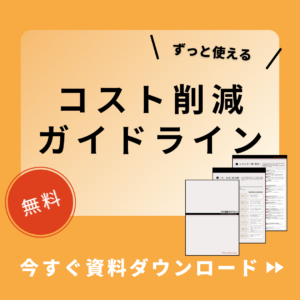「購買」は業界や業種に関わらず、企業の経営活動に不可欠な業務です。購買活動を適切に管理することで利益率の向上も見込める大切な「購買」。
この記事では、購買の意味や業務内容、一般的な役割や期待されるポイントについて、詳しく解説します。
コストマネジメントのお悩みを解決したい方へ

プロレド・パートナーズでは、コストマネジメントのコンサルティングを承ります。 自社の現状把握や、実行支援をご検討される際にはお気軽にご相談ください。
購買とは?購買と調達の違い

そもそも購買とはどういった業務なのでしょうか。
「購買」は、「買うこと」「買い入れること」を指す言葉です。個人や家庭が消費財を買うことや、企業などの組織が事業に必要な物資を買うことを指します。例えば、製品を製造している企業が、必要な材料や部品を外部から買うといったケースです。では、企業における購買について詳しく見ていきましょう。
企業における購買と調達の違い
購買と似た言葉で、「調達」が企業では用いられます。
「調達」の一般的な意味は、「必要な資金や物資を集めて来ること」です。
企業においては、製品の製造に必要な材料や部品に加え、必要な資金、必要な人材や機器・設備、ソフトウェアやサービスなど、購買よりも広い範囲に適用して用いられます。
また、購買は「買う」という手段であるのに対し、調達の場合は、レンタルやリース、一時的な契約など、必要なときに必要なだけ用意する方法を含みます。
組織によっては、「購買部門」「調達部門」というように、購買と調達の部署が分かれて存在することもあります。その場合、購買管理部門は、組織が安定して活動できるよう、必要なものを効率的に安定して買うことが役割であるのに対し、調達管理部門は、組織の動きや外部の状況をみながら最適なヒト・モノ・設備などの投入を狙う部署といえます。
購買業務の内容とフロー

次は、購買業務の内容を流れにそって解説します。
1.購買計画策定
購買にあたって、まず必要になるのが購買計画の策定です。組織の中で、どの部門が何をどれだけ必要としているのか、打ち合わせなどを通して確認します。需要の確認とあわせて、いつまでに必要なのかも確認します。
どういったものを、どれだけ、いつまでに購買すべきかを購買計画としてまとめます。購買計画としてまとめる具体的な内容としては、購買するものの、「種類」「数量」「納期」「価格」「品質」「発注方法」があります。
これらは、サプライヤー(仕入れ先)に提示する見積書作成にもつながります。自社の希望を明確に提示したうえ、最適なサプライヤーを選定していきます。
2.サプライヤー選定
購買計画をもとに候補のサプライヤーに見積書を依頼します。サプライヤーは実際にどのような条件で提供可能か、見積書を提出します。
サプライヤーによって、価格や品質、提供できる期日は異なることがあります。自社が一番優先すべきことを明確にし、それに応えてくれるサプライヤーを選ぶことが重要です。
もちろん、価格・品質・納期のすべてが高いサプライヤーがいる場合もあります。しかし、「特定の時期だから実現できた」「トラブルなどで突然通常どおりの発注ができなくなった」ということも起こりえます。パフォーマンスの高いサプライヤーとの取引を維持することは重要ですが、リスクヘッジの観点から、複数のサプライヤーと取り引きできる環境を整えておくことも重要だといえます。
3.発注
サプライヤー選定が終わり、条件の確認が済んだら、発注に進みます。見積書と同様に、希望するものの「種類」「数量」「納期」「価格」「品質」「発注方法」を明記した、「発注書」を作成し、サプライヤーに提出します。
購買計画、サプライヤー選定から時間が経っている場合は、現場が必要としているものが異なっていることもあります。
「購買計画を立てたときより希望数が増えていた」「緊急の別の需要が発生した」「予定よりも製品製造個数が減り、材料の追加が不要になった」などがその例です。
購買計画の策定時だけでなく、現場となる各部署とうまく連携をとる必要があります。定期的に必要になるものはまとめて安く仕入れる、何か緊急で必要となったときのフローを設けておくなど、工夫が必要です。
4.入荷検収
発注したものが届いたら、発注書通りのものが希望通りの数や品質であるか確認します。これを検収といいます。
壊れている、傷がついている、頼んだものと違うということも起こりうるため、必須の作業です。サプライヤーではなく、運送業者などの仲介者が原因のケースもあります。すみやかに検収作業を実施し、問題があったことを伝え、原因の特定と代替品の送付依頼などの対応が必要となります。
5.支払い処理
検収を完了しサプライヤーに通達することで、「発注通りのものを受領したので取引完了とし、支払いに進める」という意思表示をすることになります。サプライヤーから発行された請求書をもとに、契約内容と社内のルールに則って、すみやかに支払いを進めます。
6.在庫管理
検収を終え、自社に入荷したものは倉庫などで保管します。必要な量がなくなってしまうと追加の発注が必要ですし、多すぎると保管の場所をとり、倉庫保管量といった費用がかさみます。在庫を把握し、適切な量になるよう管理する必要があります。
企業における購買部門の役割

ここまで、購買業務の内容について説明してきました。続いて、購買部門の役割について説明します。
企業の購買活動において重要とされる、「購買管理の5原則」をもとに説明します。
- 取引先管理:選定段階での判断はもちろん、取引を行う中で信用できる相手先かどうか判断することも購買部門の役割となります。
- 品質管理:先にも述べましたが、購買においては品質が期待するものであるか判断することも重要です。購買部門の役割の1つといえます。
- 数量管理:必要な数量足りているか、余分に保管されスペースの圧迫やコスト増につながっていないか、管理することも重要な役割です。
- 納期管理:必要な時期に入荷できる、急ぎの事態に対応できる購買経路を持っておくことは重要です。自社にとって最適な納期を考え、また、起こりうるリスクも念頭にき、ルートを確保する必要があります。
- コスト管理:仕入価格が妥当か、より低コストで発注できないか考えることも重要です。サプライヤーを比較して、低コストを実現できる取引先に変更する手もありますし、今のサプライヤーに価格交渉するという手もあります。
購買担当者に求められること

これからさらに、購買担当者に求められることについて説明します。
サプライヤーソーシング活動
業務内容や役割でも述べましたが、購買担当者はサプライヤーとの窓口です。信用できるサプライヤーか、より良い取引を実現できる相手先はないか検討し、適正化することで、コスト削減を実現することができます。
グローバル化が進む現代においては、大企業でなくとも海外のサプライヤーと取り引きすることが一般的となっています。広い視野で、最適なサプライヤー選定を行う力が期待されます。
コンプライアンス管理
購買担当は、社内の複数部署、サプライヤーなど外部の組織とかかわります。社内のルールや適切なプロセスに則って活動する必要、社外の取引先との契約履行を守る必要があります。
業務を遂行するうえでは、自身のみでなく、関係者にもルール遵守を促さなくてはいけません。どのように進めるのが正しいのか、何を守らなくてはいけないのか、示す役割も期待されます。
サプライヤーとの関係構築
サプライヤーとやり取りの中には、価格交渉といったシビアな依頼も含まれてきます。一方で、「緊急事態なので急ぎで対応してほしい」というように、相手先に柔軟な対応を求めるお願いが必要な場面もあります。
サプライヤーとの信頼関係の構築ができる人材が求められます。
まとめ
この記事では、企業の購買活動の概要や購買部門に期待されるポイントについて解説しました。購買部門は、企業の活動に欠かせないものであり、活躍次第で組織の利益率を向上させることもあります。この記事を参考に自社の購買業務を見直してみてはいかがでしょうか?
プロレド・パートナーズでは50費目以上に専門のコンサルタントを配置し、様々な業界・業種の企業様のご相談にお応えしてきました。業務見直しやコスト削減をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
コストマネジメントのお悩みを解決したい方へ

プロレド・パートナーズでは、コストマネジメントのコンサルティングを承ります。 自社の現状把握や、実行支援をご検討される際にはお気軽にご相談ください。